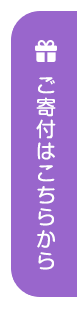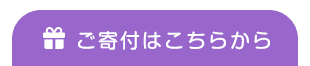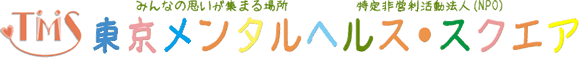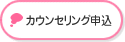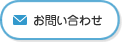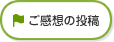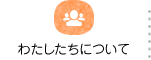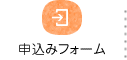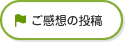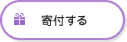みすてられ不安への対応~不安の奥にある声に耳をすます~
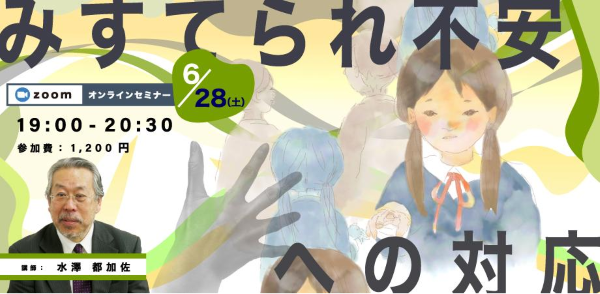
先日、カウンセラーの水澤都加佐先生を講師にお招きをしてTMSこころのセミナーが開催されました。
水澤先生はHRI 水澤都加佐カウンセリングオフィスの代表で、依存症の回復支援やDV・虐待及び家族問題、そして援助者教育など幅広い分野で活動をされていらっしゃいます。
また、「みすてられ不安」や「依存症」に関する数々の著書を出版されております。
今回のセミナーのテーマである「みすてられ不安」についてのお話しをお伺いして、私なりに感じたことをまとめてみました。
「みすてられ不安」と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか。
私は子供の頃、買い物にいった先で迷子になってしまい、「もう母と会えないのでは・・」という不安に襲われことを思い出しました。この時まさに「みすてられ不安」を感じていたのではと思います。
みすてられ不安は子供の時のみならず、恋愛や職場、あるいはペットの死や老いなどが原因で大人になってからも感じることがあり、そのままにしておくと「うつ状態」に進んでしまうケースも多々あります。
そうなってしまわないために大切なのは「自己肯定感を持つこと」だと先生はおっしゃいます。
それは「自分は世界にたった一人しかいない大切な存在」だと思うことなのですが、そのように思えるためには安心して居られる居場所が必要だと思います。
では、まわりの支援する側はどうしたら良いのでしょうか。
先生は、「相手をコントロールしない」「否定的な言動をとらない」ということが重要だと教えて下さいました。
その人がやっとの思いで話しをしている時に、「みんなそうだから・・」や「もっと大変な人がいる」などと言われたらもうそれ以上話せなくなりますよね。
さらに、みすてられ不安からの回復には、そのベースに存在している共依存や喪失感、空虚感などに着目して働きかけることも重要です。
具体的には、成長歴の見直しやグリーフワークへの取り組み、自分自身に焦点を当てて生きることを実践するなどの方法がありますが、どの場合も自己否定をするのではなくまずは認めてあげることが大切なのだと感じました。
それが「不安の奥にある声に耳をすます」ことに繋がっていくのではないでしょうか。
「みすてられ不安」は誰にでも起こり得る感情ですが、その気持ちに寄り添いながら様々な対応を適切にしていくことが大事だという理解がより深まった時間となりました。
水澤先生、大変貴重なお話しをありがとうございました。
事務局 Yoshiko T.